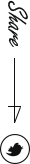私たちは生きているのである。だから哀しく愛しい。
私たちは人と出会うなか、いつしか"こころが通っている"感覚に包まれていることがあります。
「いつも微かに」あるいは「この瞬間とてつもなく」
それは、相手に同調できて寄り添えたからでしょうか?
自分を思いやって手を差し伸べてくれたからでしょうか?
じつは"こころが通った"という感覚は、そうした応報のなかにではなく、
「自分のなかに相手のこころが贈り物のように宿って、
その包みの紐をそっと解いて、相手を暖かく見つめ返す」
そんな響きあいの場面にこそあるのではないでしょうか。
本書では、こうした"内面の響きあい"を見つめて、人の《苦しみ》にアプローチします。
それも、人間が避けてとおれない「病気に見舞われる」状況で
「大切な他者」とのあいだに起きている"こころの動き"に、眼差を据えます。
病気という体の故障は医療で改善できても、
もつれてしまった不幸は、人と人の出会いのなか"こころが通う"感覚でしか、
暖かく受け留められることはないのかもしれません。