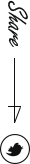写真は社会を変えられるか?
ドキュメンタリー写真やリアリズムは、
「客観的事実」を安直に反映するイデオロギー的美学としてしばしば批判されてきた。
本書は、アラン・セクーラやマーサ・ロスラー、中平卓馬ら写真家の創作・批評に加え、
フォトリーグや全日本学生写真連盟といった集団の制作や活動を
ドキュメンタリー形式の再発明と捉え直すことで、ドキュメンタリー写真概念の拡張を試みる。
20世紀の日米を中心に写真家・集団の諸実践を資本主義的近代に対する批判として、
当時の社会背景も踏まえながら丁寧に読み解いた、
このラディカルなドキュメンタリーとリアリズムの系譜の再発見は、
私たちに写真芸術の新たな視点を提示する。