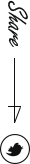分かりやすい解説とイラストで難解な薬理学を十分理解することができる。待望の改訂第3版発行。
本書は、「わかりやすい薬理学のテキスト」をめざし、
看護学生の補助教材として使用していただけるように作成しましたが、
単独でも使用できるようにすること、自習しやすいようにすること、
そして看護以外の医療系学部の学生にも利用できるようにすることを目標に内容の充実をはかっています。
いまさら述べるまでもなく、現代の医療で薬物療法は重要な役割を果たしています。
みなさんも病院を受診するとたいていの場合、薬が処方されます。
そのため、コメディカルの分野の医療系専門職をめざす学生は必ず薬理学の講義を受け、
また、各医療系国家試験にも薬の出題が必ずあります。
しかしながら、薬理学の重要性はわかっていても、薬理学を苦手科目にあげる学生が多いのも事実です。
その理由の1つは薬の名前を覚えるのが大変だということです。
現在、医療用医薬品として認可されている薬は23,000種類以上あり、
1つの総合病院(病床数400床程度)で使用されている薬は1200~1300種類あります。
そのため薬の名前を覚えるのは大変ということになります。
しかし、内科治療の90%以上が100種類の薬で行うことができるといわれています(北原光夫編:内科医の薬100 第3版 医学書院 2005年)。
また、過去10年間の看護師国家試験で、薬に関する問題は100種類の薬で約95%が出題されています(2019年)。
わかりやすい薬理学のテキストにするために、
①取り上げる薬の数をできるかぎり少なくし、
②図や表を用いて簡潔に説明し、
③補足として欄外(Note)に詳しい説明を加え、
④臨地実習で役立つように薬の一般名の後に括弧をつけて代表的な商品名を記載しました。
本書によって、薬理学が苦手科目から得意科目に変わり、
その知識を臨床の場で活用していただければ筆者としても望外の喜びです。