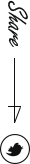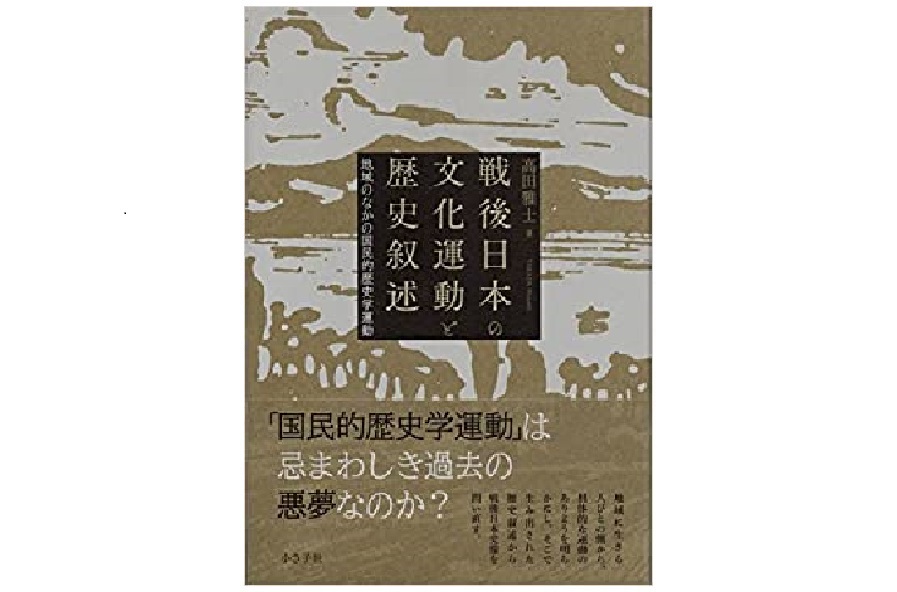「国民的歴史学運動」は忌まわしき過去の悪夢なのか?
地域に生きる人びとの側から、具体的な運動のありようを明らかにし、
そこで生み出された歴史叙述から戦後日本史像を問い直す―。
敗戦直後に歴史研究者の石母田正が、民衆自身の手で
「村の歴史・工場の歴史」を主体的に書いていくことを呼びかけはじまった「国民的歴史学運動」。
1950年代に入って歴史学界を中心に大きな盛り上がりをみせたが、
1955年の日本共産党の政治方針・文化政策の方向転換をきっかけに
運動は「挫折」し、「傷痕として封印」されたとされる。
今では、歴史学が政治に従属した悪しきエピソードとして
わずかばかり言及されるのが一般的である。
本書は、地域に生きる人びとが主体的な歴史意識を形成していくうえで、
国民的歴史学運動の経験はどのような意味を持ったのかを明らかにする。
京都府南部や奈良を主たるフィールドに、
地域に残された新資料を掘り起こし、聞き取りなどの手法も駆使して探究。
さらに、人びとの「その後」のあゆみにも目を向け、地域社会の変容と関わらせながら、
彼らがどのように新たな運動に取り組んでいったのかをとりあげることで、
国民的歴史学運動の有した意義をあらためて地域や人びとの側からとらえ返す。